有識者インタビュー
灯台建築

灯台には立地、構造、工法、素材と、近代建築技術の歴史が詰まっている
東京工業大学名誉教授 藤岡 洋保
建築物として見る時、立地、構造、工法、素材という4つのポイントがあります。立地ですが、これを19世紀後半に決めたのは海外列強。定期航路を日本につなげるためです。明治になると海軍と政府が決めます。当時は船こそが人やモノの輸送の要で、各地からその安全航行のための灯台設置の請願が帝国議会に出されていました。
構造と素材は、石造、レンガ、鉄、木造が明治期のもの。鉄筋コンクリートはその後です。灯塔は、高さや建つ位置によって構造が使い分けられていますし、石を使う場合は船で運ぶため、その産出地も海に近いところに限られていました。鉄製の灯塔や霧信号所には格子状の鉄骨に鋼板をリベットで張りつける、日本独自の工法が見られます。
灯台は一見単純ですが、建設地の状況や材料、灯塔の高さに応じていろいろな工夫がされています。
役割

灯台には船舶の安全を守るとともに日本の経済水域を示す重要な役割がある
日本航路標識協会専務理事 池田 保
航路標識とは、灯光、形象、彩色、音響、電波などの手段により、沿岸水域を航行する船舶が指標とする施設のことです。岬の先端などにある「灯台」、岩礁などを知らせる「灯標」、航路などを示す「灯浮標」が代表的なものです。情報を伝える光り方には不動光、明暗光、せん光など8種類があり、それぞれ設置場所や目的で使い分けられています。
船舶が目的地に安全かつ効率的に航海するためには航海計画を立て、コースラインを選定しますが、沿岸を航行する場合は主要な変針点に設置されている灯台などが指標となります。また、沿岸に設置される灯台は遠く沖合を航海する船に陸地を認める機能を持つ標識でもあります。
つまり灯台は自船の位置を目視で確認する存在であると同時に、航海者に安心感を与えるという重要な役割が備わる施設なのです。その価値は航海計器の発達した今も変わることはありません。
技術

時代の最先端技術とともにあった灯台、現在もまた研究・開発が進む
海上保安庁交通部整備課長 菊田 信夫
灯台はいつの時代も最先端技術とともにありました。光源で言えば明治期は油を燃焼する灯器から始まり、ガス、電気へ。以降、白熱灯の時代を経て、より省電力な放電灯となり、現在の大型灯台はメタルハイドランプです。また大光力を必要としないものはLEDが用いられます。
灯台の運用・メンテナンスは、明治期は油を使っていたことから有人管理が不可欠でした。それが電化の進展や技術の進歩により、点消灯の自動化、電源障害時の予備電源装置などの機器が開発され、徐々に無人化・自動化への整備が行われています。
現在、最も新しい技術と言えるのはパワーLED。大光力を得られることから大型灯台や照射灯への活用を図っています。またドローンを活用した点検の実用化やウェアラブルカメラを活用した遠隔支援の実用化に向けた研究も進めています。
民俗

海の安全を守り祈りの空間であった場所を、現代に継承する灯台
民俗学者・神職橋本 裕之
近代以前、日本近海の航海者や漁民にとって、海上交通安全には2つの側面がありました。一つは「山当て」と呼ばれる、現在地を確認する技術的な側面。もう一つは天候や海流など自然という人智を越える存在に対する畏敬の念から生まれる、祈りの側面。この2つの対象となったのが、例えば沿岸部の小高い山に設置された神社です。
2つのうち技術的側面は近代以降、「灯台」が担ってきました。では、祈りの側面はどのように継承されるのか。現代においても「山当て」の技術は活かされ、「灯台」はその対象です。そうであるならば「灯台」が「祈りの空間」を継承することもできるのではないでしょうか。例えば岩手県普代村で続く「鵜鳥神楽」は、神様が人々を訪ね巡行する神楽。その中に「灯台」を含めることで「祈りの空間」となり得るのです。
旅

灯台を目指すと、旅の目的が叶う至福の自分時間が待つ、とっておきの場所
フリーペーパー「灯台どうだい?」編集長 不動まゆう
人はなぜ旅をするのでしょう。目的や興味は人それぞれですが、共通して求められるのは「非日常感に身を置きリフレッシュする」や、「新しいモノやコトに出会う・体験する」だと思います。では灯台旅で得られるものは何かというと、到着時の達成感、爽快な景観、灯台が背負う歴史の発見、点灯時の感動、漁港での食事などが挙げられ、充分に旅の醍醐味を網羅しているのです。また自由な「楽しみ方の創出」もできます。私は灯台について理解を深めることが喜びなのでフィールドワークを行います。わずかに残った灯台守の官舎跡から間取りを推測。ここに生まれていたらどんな人生だったかなぁと想像する。これが私の至福時間。他にも写真を撮ったり、ピクニックをしたり、海に向かって歌ったり。灯台は一人ひとりの楽しみを受け止める懐の広さがありますね。
地域政策

地域のシンボルである「灯台」はシビックプライドの対象となり得る存在
関東学院大学准教授 牧瀬 稔
「シビックプライド」という言葉があります。自分自身がかかわって地域を良くしていこうとする、当事者意識に基づく自負心のことですが、建築学からスタートした言葉ゆえ、その対象となるのは目に見えるもの。「灯台」はそこに当てはまる。
そして「シビックプライド」を持つことで、「活動人口」が増えていく可能性が高まります。「地域に対する誇りや自負心を持ち、地域づくりに生き生きと参加する者」と定義しますが、これが重要。最近は地方都市の人口減少が叫ばれていますが、大事なのは「活動人口」の数。快活な人の割合が高いことがポイントなのです。
そのためには共有、共感、共創が大事で、さらに共助と共生の5つの「共」が地域を元気付けると考えます。地域のシンボルである「灯台」は、活動人口を増やし、シビックプライドの対象になり得るものだと思います。
灯台史

平安時代から現代まで時代とともに進化し、日本の海を守ってきた
燈光会専務理事 今井 忠義
「続日本後紀」に遣唐使の時代、篝火をたいた記録があります。江戸時代には石を積み重ねた上に木造建築を設置した「灯明台」の中で油を浸した灯芯を燃やしました。そして幕末から明治にかけて西洋式の灯台が作られていきます。
当時も時代の最先端の技術が使われていましたが、それは今も変わりません。例えば太陽電池を用いた灯台が初めて登場したのは1959年。宇宙開発技術からの転用でした。また2009年頃から家庭に普及し始めたLEDは1989年から利用しています。
灯台の歴史を語る上で欠かせないのが「灯台守」です。点消灯の操作、レンズの回転作業からメンテナンスまで行い、灯台の円滑な運用に欠かせない存在でした。そんな彼らの生活は厳しく、雨水を溜め、魚を釣り、畑を耕し、文字通り生きるための生活をしていました。
また第二次大戦中、灯台守は無線連絡員であり、空襲の監視も行っていました。灯台は攻撃目標ですが彼らは避難もできず、全国で殉職者が相次いだ記録も残っています。そんな灯台守がしっかりとメンテナンスをしてくれたからこそ、明治期に作られた灯台を今も見ることができるのです。
近代外交史

幕末から明治にかけて日本に入ってきたものは灯台というハードだけでなく、ソフト面も重要
和歌山県立文書館研究員 平良 聡弘
欧米列強と条約を結び開国した幕末の日本。その日本沿海はダーク・シー(暗黒の海)と呼ばれ、航海上危険視されており、1860年代半ばには、洋式灯台を建設するよう海外からの要求が高まっていました。折しも、江戸幕府は下関事件の賠償金支払いの猶予を求めており、その代償として欧米列強が提示したのが洋式灯台の建設でした。1866年、幕府の責任で灯台をつくることが決定されました。
そして和歌山にも樫野埼・潮岬、および友ヶ島に洋式灯台がつくられことになり、イギリス人技術者が派遣されてきます。それに対応したのは紀州藩当局ではなく、地元の役人でした。だから当時のリアルな記録は藩庁には残らず、現地、例えば串本にある。いつ上陸して、何を提供したということが、事細かく書き留められています。
建設には地元民が駆り出されますが、当時の日本人と欧米人の考え方の違いは大きく、軋轢も生まれました。しかし灯台建設の現場は、現地の人々にとってヨーロッパのスタイルを学びうる場になったのではないでしょうか。このようにハード面だけじゃなく、ソフト面でも新しいものが広がり、日本の近代化が進んでいったのだと思います。
地域グローバル史
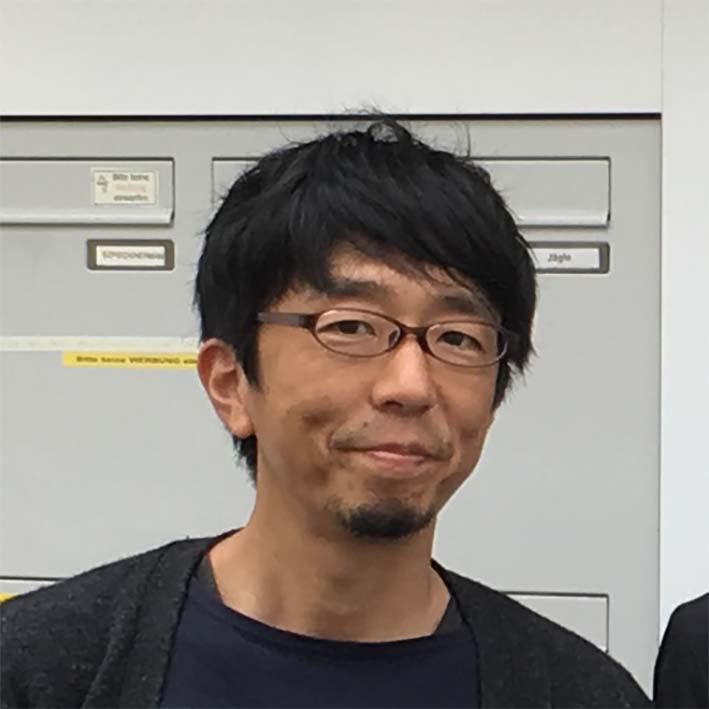
開放系のメッセージを発信し、地域を世界と結びつける
金沢大学新学術創生研究機構准教授 谷川 竜一
灯台は、遙か海に向けて光を送る陸の施設であり、すぐ傍にはいない「誰か」のための施設です。その光は危険な海の上では生死さえ左右する重要なもの。でも届いたかどうかはわからない。
海の上に「いるかもしれない誰か」が、受け取ることを「期待」して光っているのです。
そんな灯台の「未完のコミュニケーション」、あるいは灯台という「メッセージが開放系で終わるような場」が、私たちが灯台に惹きつけられる理由ではないでしょうか。開放系であるからこそ、そこに様々な人々が多様な願いや希望を重ねて一方的に送ることが可能であるし、他方でそれを時に私たちが予測し得ない未知のものと灯台は繋げてくれるからです。
灯台のような公共財は、それを使う人を限定しませんし、常に使われるとも限りません。大切なことは誰かが必要としているかもしれない、という開放系の想像力。そして灯台が開放系のコミュニケーションを担う建造物であったことが、その地域をグローバルに結びつけ、様々な人や文化、世界観の出会いを導いたのだと思います。
そういった見方をしていると、灯台はもっと面白く見えてくるのではないでしょうか。
地域振興

地元に愛されているのは航路標識以上の価値が灯台にはあるから
日本交通公社観光政策研究部 戦略マネジメント室研究員 小坂 典子
学生の頃から島巡りを楽しんでいたので、灯台の思い出は多いです。地元の方と話すと、みなさんの思い出の中にも必ず出てくる。灯台がアイデンティティの一つになっていると感じます。モノというより、思い出そのものなのです。
個人的なイメージは2つあります。例えば寂寥感を感じるところ。昔はもっと栄えていただろうな、と。もう一方はまちに近く、地域の生活とともにある灯台。そんな風景を見て思うのですが、地元の人は機能を重視していないんじゃないでしょうか。みなさんの灯台への思いは、モノというよりヒトに対する感情に近い。だからこそ地方活性の視点で見ても、灯台はこれから活用していくべき存在なんです。人の思いが蓄積されているものがなくなったら、空っぽになってしまう。灯台があることで他の人とのかかわりが生まれたりしたのですから。
大事なことは灯台が地域の人にとってどんな存在だったかを、外の目線でも掘り起こすこと。そして継続して活用することです。そのためには地元の産業と結びつくことは重要。また灯台はアクセスに難がある場所が多いので、その場所ならではの価値を作ることも大切です。決して簡単ではありませんが、例えば地元の特産品に付加価値をつけるやり方は今や一般的です。新しいアイデアを取り入れながら、今に生きる「灯台」を一緒に生み出していきたいです。
ローカル鉄道

近代日本を作ってきた灯台とローカル鉄道を新たな“憧れの場所”に!
えちごトキめき鉄道代表取締役 鳥塚 亮
ローカル鉄道と近代灯台は歴史が同じくらいですよね。そこに共通点があると思います。世の中が変化し、ローカル鉄道も建設当初の役割は終わっている。そして沿線の町を見渡すと廃れているんです。では、町もローカル鉄道同様に役割が終わっているかと言ったら、そうではありません。時代に合わせた使い方があるはずなんです。だから我々ローカル鉄道もイベント列車を走らせたりして、多くの方に振り向いていただくためのツールにしようとしている。
灯台も、航路標識としての役割が終わったとしても別の方法があるはずです。個人的なイメージで言うと、灯台は先端にありますよね。そういう「最果て」に行ってみたいと思う人は多い。それに、そもそも「海」そのものに価値があって、そこにつながっているのが灯台。その景色には普遍的な価値があると思います。
だから、灯台が憧れの場所になればよいんです。「やっと来れた」と思える場所にする。例えば買物には日用品と買い回り品の2 種類がありますよね。買い周り品は趣味のものだったりするから滅多に買わない。でも本当に欲しければ、多少高くても手に入れます。「憧れの場所」とは、そういうこと。人生にはそういうことが必要だし、僕らローカル鉄道が目指しているのも、「憧れの場所」になることです。灯台にも同じことが言えるのではないでしょうか。
グランピング

眺めていたい灯台はキャンパーにとっての焚き火のような存在
ABC Glamp&Outdoors 代表取締役COO 吉村 司
10年ほど前に淡路島でキャンプ場を始めたのが我々のスタート。漁港の隣だったので、灯台はいつも見えるところにありました。キャンプをしながら灯台を見ていると、「焚き火のようなものかも」と思ったりします。暖を取ることと船の安全を守ることが本来の目的ですが、同時にずっと眺めていたい存在なんです。そういう意味でも非常に面白い観光資源だと思います。アウトドア事業の観点から言えば、ロケーションそのものが魅力的ですしね。
ただし灯台でキャンプをしようとしたら検討材料は多い。トイレやシャワーをどうするか? 食事は? 安全面や天候の変化に対する危機管理は? 筋金入りのキャンパーであれば必要はないかもしれませんが、我々が手がけているのは、一般の方に自然を楽しんでいただくグランピング。そのための最低限の設備は必要です。ただ考え方次第でもあります。日本には3000もの灯台があるんですよね。そのいくつかをキャラバンする企画であれば、対応できる可能性も高くなる。灯台をモニュメントとしたグランピングパークのようなものも考えられます。
そう考えると灯台には観光資源としての可能性が大いにある。それに多くの人は、灯台のある風景をすぐに思い浮かべることができると思うんです。そのイメージに応えられる世界観を提供できれば、すごく面白いことができるのではないでしょうか。
映画・ドラマ・ロケ

灯台という存在が映画やドラマの物語を際立たせる
雑誌「ロケーション・ジャパン」編集長 山田 実希
灯台に行けば、きっと綺麗な風景があると思えるんです。自分が出かけた中で印象に残っているのは角島灯台(山口県)。『四日間の奇蹟』という映画のロケ地ですが、作品に教会として登場するのが灯台の公衆トイレ。びっくりしましたね!その時に隣接する資料館を訪ね、歴史を知り、灯台への興味が増しました。理由は「人を感じた」ということ。ただの建造物ではなく、「人を守るために光を灯している」ということに温かさを感じました。
映画の舞台として印象的だったのは『悪人』。ロードムービーですが、その終着地点が大瀬埼灯台(長崎県)。同作の李相日監督にインタビューした際、「逃亡劇なので最後に行き着く象徴的な場所が必要でした。あの灯台でなければ成立しなかったと思います」と。そういうストーリーを際立たせる存在として、灯台は魅力的だと思います。また歴史的建造物としての魅力もありますよね。映画やドラマには時代考証が欠かせませんが、「この灯台は何年製です」とわかれば、製作者のイマジネーションも広がると思います。
そして、なんと言っても灯台のある風景は絵になる。ロードムービーであれば、灯台を舞台にするだけで説明しなくても最果て感が演出できる。灯台はドラマが生まれやすい場所だと言えます。
サイクリング

景色を楽しみながら走る自転車は灯台巡りに最適!
自転車業界誌「月刊サイクルビジネス」編集統括 前田 利幸
自転車と海岸線はセットのようなもの。メッカと言って良いと思います。ただ、これを地域活性や灯台の盛り上げにつなげるのであれば、人をより集めることが必要。愛知県知多半島で開催されている伊良湖岬灯台を巡るイベントは有名です。観光業者とも連携し、毎年大いに盛り上がっています。
もちろん、イベントがなくても灯台と自転車の親和性は高いと思います。自転車の魅力の一つは風景を楽しみながら移動できること。景観を楽しむ意味では、非常に優れた交通手段なんです。だから海岸線は人気がある。そのことをもっとPRすべきですね。その意味では今は大きな流れの中にあります。一つは2016年に施行された自転車活用推進法。国民の健康推進と環境配慮の面から自転車を活用しようというもので、各自治体が自転車を活用した観光などを企画・実施すると補助金助成がある。これを活用する機運はあるのですが、地域によっては自転車に不向きな場所もある。それをフォローするのが「Eバイク」という、スポーツタイプの電動自転車。一般的な電動自転車よりパワーも電池寿命も長く、観光向き。そんなEバイクのレンタルがあれば、もっと気軽に灯台サイクリングが楽しめると思います。灯台と自転車という組み合わせで楽しむ人が増えるのは、とても意義のあること。どんどん展開していって欲しいですね。
サブカルチャー

コンテンツ化することで、若い世代と灯台を一緒に盛り上げていく
大阪成蹊大学 芸術学部長映像監督 糸曽 賢志
灯台を活用し、さらなる活性化を生み出していくために「コンテンツ化」を提案しています。例えば、2015年のゲーム配信からスタートした「刀剣乱舞」は多くの女性ファンを獲得し、社会現象と呼ばれるほどのメガコンテンツとなりました。刀は全国に点在しますが、それを「コンテンツ化」することで点が線となり、大きなムーブメントとなったわけです。こうした動きは、灯台でも作り出すことができるのではないかと考えています。一方、現在は大学で教鞭を取らせていただいておりますが、そこで感じるのが「若者は未来に希望を抱いていない」ということ。その背景には、成功体験が少ないということが挙げられます。そこで彼らの自信になって欲しいと考え、2019年度には国内51基の灯台をアニメーションイラストにした絵葉書を学生とともに制作。「灯台を巡ろう!キャンペーン」のノベルティとして配布いただくことで、メディアにも取り上げられました。こういう実績が彼らの自信に、ひいては希望につながっていくと思います。
今後も灯台それぞれが持つ歴史やストーリーを若い世代とともにコンテンツ化することで、灯台の文化価値創造に貢献していきたいと思っています。
食文化

灯台は地域の文化と食を育む大切な要素
食文化研究家 向笠 千恵子
私のテーマは「食」ですが、取材や調査ではそれが生まれた風土や生産者の思い、歴史を理解したいと思うので、時間の許す限り周辺を見て回ります。もちろん灯台もその対象。忘れがたいのは新人の頃に出かけた島根県の出雲日御碕灯台。滋賀県にルーツを持ち、島根で親しまれている「津田かぶ漬」を取材したのですが、干している津田かぶを撮影した時、後方に灯台が見えたんです。どうしても近くから見たくなり、タクシーで駆けつけました。
食の歴史… 北前船と食の街道について調べると、例えば北海道江差町の鴎島灯台のある港などから昆布やニシンが西回りで全国に広がった歴史がありますよね。また灯台の麓に漁村があれば、独自の魚食文化が栄えていることもあります。和歌山県雑賀崎の「灰干しさんま」は対岸の四国鳴門で発明された「灰干しわかめ」を応用したもの。この「灰干しさんま」を作っている集落の先端に無人の雑賀崎灯台があります。私が尋ねた頃はあまり活用されていませんでしたが、最近では灯台近くの港でフリーマーケットが始まり、賑わっているそうです。
全国の漁港や港町を訪ねると、その近くには灯台がある。そして地域のみなさんと話すと、記憶の中に必ず灯台が息づいている。地域の文化はそうやって育まれるもので、それは食も同じ。その意味でも灯台をいつまでも守り伝えていただきたいです。
